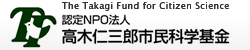アフリカ小農主体の開発・援助に関する調査研究〜日本社会に向けた提言
| モザンビーク開発を考える市民グループ |
研究成果発表会配布資料[pdf] |
|
| 大林 稔 さん | ||
| http://mozambiquekaihatsu.blog.fc2.com/ | ||
| 70万円 |

8月中旬に南アフリカで開催された「民衆法廷」の様子。南部アフリカの多くの国の人たちが参加した。「略奪を止めろ。アフリカは売り物ではない」というバナーが掲げられている




モザンビークの首都マプートで開催された「第三回 3カ国民衆会議」および「3カ国民衆会議キャラバン ナカラ回廊沿いコミュニティの訪問」の様子(2017年10月)。本研究グループの渡辺直子(JVC)は、現在モザンビーク政府によってVISA発給が拒否されていたため、渡辺の席は空席となり、代わりにネームプレートが置かれた
研究の概要
2016年12月の助成申込書から
本研究は、 2015年度の助成研究「アグリビジネスによる土地収奪に関するアフリカ小農主体の国際共同調査研究―モザンビーク北部を中心事例として」の成果をもとに、 2016年度には「日本の官民による「回廊開発」がモザンビーク小農の暮らしに及ぼす影響に関する研究―小農主体の調査・政策提言を目指して」との題目の研究に発展させる形で実施してきた。
これまでの研究活動では、アフリカ、とりわけ日本の官民が積極的に進出するモザンビーク北部に注目し、「経済回廊開発」の促進によって、アグリビジネスをはじめとする大規模経済投資による土地収奪(ランドグラブ)がもたらす影響について、小農主体の調査・研究・提言活動を行ってきた。2年間の助成によって、 (1) 土地収奪の背景と実態、 (2)「経済回廊開発」の実態とその影響、 (3) 日本の官民の関与の情報収集と整理、 (4)これらに関する調査・研究・政策提言における地元住民(とりわけ圧倒的多数を占める小農)の主体的な活動の支援が可能となった。
3年目にあたる本年は、これまでの日本の市民グループとモザンビーク小農による国際共同調査研究の成果を踏まえ、日本政府・企業・学術界・社会に対して、小農の視点から問題提起を行い、「日本によるアフリカでの開発・援助に関する実態」について、市民科学に基づく調査結果を提供し、ともに考えてもらう機会を提供したいと考える。そのことによって、小農らとともに、これまでの蓄積を政策に反映させる努力を最大化させる。
中間報告
2017年10月の中間報告から
これまでの研究活動では、アフリカ、とりわけ日本の官民が積極的に進出するモザンビーク北部に注目し、「経済回廊開発」の促進によって、アグリビジネスをはじめとする大規模経済投資による土地収奪( ランドグラブ) がもたらす影響について、小農主体の調査・研究・提言活動を行ってきました。
3年目にあたる今年度は、これまでの日本の市民グループとモザンビーク小農による国際共同調査研究の成果を踏まえ、日本政府・企業・学術界・社会に対して小農の視点から問題提起を行い、「日本によるアフリカでの開発・援助に関する実態」について、市民科学に基づく調査結果を提供し、共に考えてもらう機会を提供したいと考えています。そのことによって、小農らとともに、これまでの蓄積を政策に反映させる努力を最大化させます。
今年度は、4月末のモザンビーク北部住民11名による、JICA環境社会配慮ガイドラインに基づく異議申し立てが行われたことを受けて、次の4つの活動を行いました。
(1)日本政府・企業向けの政策提言活動の強化
外務省、財務省(JBIC/企業)、JICAとの定期協議会で、対アフリカ・モザンビーク政策に関する問題提起。モザンビークで開催されたTICAD閣僚会議に向けた支援。
(2)学術界(国際・国内)への問題提起
食と農に関する国際学会でのワークショップ開催(ブラジル・モザンビークの小農運動と共催)や土地問題に関する国際学会に出席し議論に参加。「農民主権」に関する勉強会の開催。
(3)一般向けの広報
ブログ、Facebook、Twitter などの運営。Change.org とのコラボレーション。
(4)北部住民の異議申し立てへの支援
公正なる審査の環境を確保するよう要請文を送付。申立人の依頼を受けた資料提供などの支援。
なお、8月下旬にモザンビークで開催されたTICAD閣僚会議で、現地農民運動や市民社会組織、日本のNGOらと一連の政策提言活動(イベント・声明発表)を予定していました。また、その後に2週間程度の現地調査を、モザンビーク北部の農民組織と予定していたところでしたが、モザンビーク政府によって担当者(渡辺直子)のVISAの発給が拒否されたために、これが不可能となりました。
この件について、渡辺直子がモザンビークに入国できるように求める署名活動を行ない、9 月末現在で約4400筆の署名が集まっています。(WEB サイトでの署名や進捗状況については、Change.org の以下のページをご覧ください。http://bit.ly/2v4IP8U)
結果・成果
完了報告・研究成果発表会資料より
本研究グループは、3年間のモザンビーク小農運動や市民社会組織との国際共同活動を経て、「小農主体」の調査研究・政策提言・発表を通じた、国内外の政策・ディスコース転換に尽力してきました。その結果、当初の「小農に調査ができるのか、学会で発表などできるのか?」といった偏見を覆し、むしろ当事者だからこその視点と手法で行う実証的な調査の有効性を示すことが可能となりました。
本年度はこれらの蓄積・知見を、多くの出版物やメディアで取り上げてもらうことができ、これまで以上に成果の社会的還元が可能となりました。また情報開示請求や録音データなどによるファクトに基づく政策提言・交渉を粘り強く行い続けた結果、政策面での変化の兆しが現れつつあります。
また、4月末のモザンビーク北部住民11名によるJICA環境社会配慮ガイドラインに基づく異議申し立て、8月にTICAD(アフリカ開発会議)閣僚会議(モザンビーク)や民衆法廷(南アフリカ)、第三回「3カ国民衆会議」(モザンビーク)が開催されたことを受けて、次の7つの活動を行いました。
1)政策提言活動の強化
2)学術(国際・国内)への問題提起
3)一般向けの広報(「国連小農の権利に関する宣言」ドラフトの翻訳を含む)
4)北部住民の異議申し立てへの支援
5)国際会議でのアドボカシー活動機会の活用
6)第三回「3カ国(モザンビーク、ブラジル、日本)民衆会議」への参加
7)国会・情報開示請求への対応
これらの活動を通して「小農を主体に」からより大きく足を踏み出して、「小農から学ぶ、学び合う」という関係を、より日本社会の広い層・当事者と育めるような機会を創出することが重要になっていることが分かりました。これまで3年間の国際共同研究の成果を踏まえ、2018年11月に「3カ国民衆会議」を日本で開催します。
その他/備考