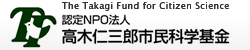原子力は温暖化対策にならない むしろ新規原子力は温暖化を悪化させる
| グリーン・アクション |
2009年度完了報告[pdf20kb] 2009年度完了報告[pdf20kb] |
|
| アイリーン・美緒子・スミス さん | ||
| http://www.greenaction-japan.org/modules/jptop1/ | ||
| 50万円 |
研究の概要
2008年12月の助成申込書から
人類の文明が生み出した「地球の温暖化問題」の解決は、かつてない規模で共通に取り組まなければならない重要かつ緊急の課題である。この解決を大きく阻むのが、「原子力は温暖化問題の解決に繋がる」という誤った宣伝と他国のエネルギー政策に悪影響を及ぼす原子力の売り込みである。
しかし、近年海外では「原子力は温暖化問題の解決に繋がらない」という多数の分析結果が出され、「新たな原子力発電施設(「新規原子力」)の建設はむしろ温暖化対策を悪化させる」という結論にまで至っている。
だが、日本ではまるで鎖国のように、この情報が普及していない。そこでこの調査研究では、まず海外の情報を収集し、次に国内のエネルギーや原発問題に取り組むNGO・研究者、市民・マスコミ、そして議員など政策決定者にこの情報を普及し、最後に様々な分野で話題になるよう議論を巻き起こすことを目的とする。
鍵は日本のNGOとエネルギー問題に関心を持っている研究者や経済学者などがこの問題を取り上げやすいようにすることである。グリーン・アクションは、ファシリテーターとしての長年の実績を生かして、情報交換と協力をしながらこの問題にメスを入れていく。
以上を若い活動家を育てながら行っていく。
【 この助成先は、2010年度にも同様のテーマで助成を受けています → 2010年度の助成事例 】
中間報告
2009年10月の中間報告から
この調査研究計画の目的は、「原子力は温暖化問題の解決には繋らない」と「新規原子力はむしろ温暖化対策に逆効果を与えてしまう」という情報を日本に普及させ、日本国内に議論を巻き起こすことです。これを若い活動家を育てる仕組みで活動を行う計画です。
ヨーロッパと米国のNGOと直接連絡し、最新の資料を取り寄せました。またグリーン・アクションのHPを通じて、国内に海外のNGO の「原子力と温暖化に関する国際アピール」という署名のサイバーアクションも紹介しています。
「世界の原子力ルネサンスは起きていない、むしろ原子力は斜陽しつつある」という最新のドイツ政府委託報告書、また「新規原子力は温暖化対策に逆効果を与える」などを示している資料(米国のRocky Mountain Institute、憂慮する科学者同盟(UCS)の資料)などを和訳しました。この和訳をもとに、一般市民向けのチラシの作成を進めてきました。
7月末まで民主党国会議員本人に直接働きかけました。(その後大臣3名、副大臣1名などとなる)。選挙後に会う約束も一部取り付けています。現在その働きかけを継続中。
学生を対象に大学の授業でこの問題を取り上げました。大学での勉強・ディスカッションを一部学生と企画中。日本のNGOと連携して勉強・討論会の企画も進めました。マスコミと連絡を取り、英文の資料と和訳を提供しました。
若い活動家と会い、この問題を展開して行く方法を話し会い、研究者・活動家と話し合い、参加を働きかけて来ました。
COP15に向けての国内NGO企画ミーティングに参加し、この問題を取り上げることを話し合いました。
結果・成果
2010年5月の完了報告から
原子力発電は温暖化対策の「切り札」になりうるのかについての情報や分析は、海外には豊富にあり、原子力推進の機関でも、「目から鱗」となる情報が豊富にみられた。具体的には、世界銀行(World Bank)、エネルギー関連の研究所、スタンダード&プアーズなどの金融情報・分析サービスを行っている会社、シティグループ、原子力産業の情報を取り扱う出版物、アジア・ヨーロッパ・米国の大学に所属する学者の研究そしてMIT(マサチューセッツ工科大学)のような大学上げての研究報告、大手環境団体、ドイツ政府のような公的機関の委託報告書、IEA(国際エネルギー機関)などが発行している情報である。
原発の反対運動を主とするNGOを対象に、「原子力は温暖化対策にならない、むしろ新規原子力は温暖化を悪化させる」について院内集会、メーリングリスト、メルマガなどを通して伝えていくことが出来た。また気候変動問題に取り組む主な団体と協力し、与党に働きかけ、この問題について情報伝達を行った。また、国際的にこの問題に取り組む研究者と共に、一対一で与党議員と会い、今後の活動提案も含め情報提供と議論を行うことができた。さらに、グリーン・アクションのHPを通じて、海外のNGOの活動、たとえば「原子力と温暖化に関する国際アピール」という署名のサイバーアクションを紹介するなど、海外の活動に日本からも参加できるよう紹介することができた。一般市民への普及をめざして、マスコミと連絡を取り、英文の資料と和訳を提供した。学生を対象に、大学の授業・大学主催の企画でこの問題を取り上げた。
ヨーロッパと米国のNGOとの関係については、直接連絡を取り合い、最新の資料を取り寄せる過程を通して、今後も調査研究の課題を続けるための協力・連携体制を整えることが出来た。
その他/備考