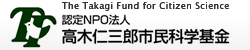緑化地区と都市貧困層の立ち退き政策における調査研究:北ジャカルタのベルシ・マヌシアウィ・ダン・ベルウィバワ公園の事例
| インドネシア環境フォーラム(FoEインドネシア) | ||
| カリサ・カリド さん | ||
| 10万円 |

「緑地化」されたエリア

土地の利用を禁じる政府の立て看板
研究の概要
2008年12月の助成申込書から
インドネシア首都ジャカルタのスラム街では、インドネシア政府が2007年以降、大気汚染や洪水を理由に「緑地化」の必要性を掲げて、住民の立ち退きを進めています。こうした緑地エリアは店頭やモールといった商業的な利用に転じることが多く、政府が都市を近代・快適化するために「環境問題」を使って貧困層を立ち退かせるといった人権侵害が生じていることが考えられます。本調査では、こうした政府による立ち退き政策の実態を明らかにし、市民社会がどのように対処すればよいのかを分析し、政策提言を行います。
調査実施期間は、2009年1月〜2009年4月です。
中間報告
結果・成果
大都市の衛生問題を解決するために、インドネシア政府はジャカルタにおいて環境回復という名のもとに「緑地化」を進め、貧困層の人々の立ち退きを進めています。本調査研究では、「環境の重要性」と「人々の基本的人権」のせめぎ合いの中で、権力がいかに貧困層の人々の生活圏に介入し、管理するかに注目しました。事例として、ベルシ・マヌシアウィ・ダン・ベルウィバワ(BMW)公園で2008年8月24日に5,000人の警官を導入して実施された立ち退きを取り上げました。結論として、緑地化の重要性を掲げて貧困層の立ち退きを実施しても、環境などの都市問題の解決にはならないということです。都市の環境問題は、「不法滞在者」の増加によって生じるという単純なものではありません。市民に対する介入および管理は、土地を含む生活の源の確保における公平性を実現するために行われるべきです。
現在の政府による経済政策は消費者層を支えるための搾取的なもので、資本家を権力者とする現状を変える必要があります。国家政策によって地方の村から都市への人口流入に対応する必要があります。干ばつや沿岸開発のために土地や生活の糧を失うような地方の農村の危機が解決すれば、結果として都会の問題も収束するでしょう。当面の解決方法として、緑地化政策の理念を人々の安全や生産性、福祉および自然の持続可能性を保障するものと位置づけて、緑地化と貧困層の人々の居住を統合することを戦略的な解決策とすることができると考えます。緑地化された土地を商業的な売り物とするのではなく、貧困者層の人々が土地の管理者となるモデルを実施することもできるのです。
その他/備考