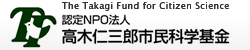東海第二原発廃炉にむけての活動
| リリウムの会 |
研究成果発表会配布資料[pdf] 研究成果発表会配布資料[pdf] |
|
| 岡本 孝枝 さん | ||
| http://blogs.yahoo.co.jp/liliumnokai | ||
| 30万円 |

7月26日に開催された「とうかい環境フェスタ」では、村役場の駐車場に核のゴミMAP を展示。

2014年9月版の「核のゴミMAP」。
研究の概要
2011年12月の助成申込書から
私たちは東海村に住むごく普通の住民だが、3.11震災後に、原発を取り巻く真実に気づき、安心して住み続けられる故郷を未来に残すために、東海第二原発の廃炉に向けて活動している。活動内容としては、昨年に引き続き、原発関係の映画を自主上映会や講演会を企画している。
一方、昨年提出した請願に関して村会議員全員に公開質問状を送り、その返答を全村配布した。この請願は5月に不採択となったため、再びすぐに新たな請願を出した。
また「脱原発をめざす首長会議」の東海村での開催を陰で支えた。こうした活動を通して、常にどうしたら原発立地自治体が原発依存から抜け出られるかを模索している。その一環として、行政にも意識を向け、4月に「ミニ村政懇談会」を開き、村の行政の姿勢に迫った。また村議会議員との面談、議会傍聴などの行動も積極的にしている。
9月の東海村長選挙には村上氏(前東海村長)に再出馬を要請したが、結果として村上氏は出馬を断念するに至った。村民がもっと原発の危険性にも関心を向けてほしいとの考えから、村上氏と共に住民参加型の塾を新たに立ち上げ、今後も脱原発・脱被ばくの意識を広める活動を続けていく。
また、村民に積極的に情報提供をしようと、チラシ配布活動(「リリウム通信」や「核のゴミマップ」)にも取り組んでいる。
中間報告
2014年10月の中間報告から
東海村には、東海第二原発だけではなく、再処理施設など危険と隣り合わせの施設が数多くあり、高濃度の核廃棄物も大量に保管されています。しかし原発立地自治体が等しくそうであるように、村では原発に依存する人々の発言力が大きく、原発に異を唱える発言には勇気が必要です。しかし福島原発事故以後、私たちは、原発の真の危険性と反倫理性に気づき、社会のパラダイムが変わったと認識しました。そして、今ここで東海第二原発を再稼動させないように全力を尽くそうと、行動し続けています。村の行政は原発や核燃料などの情報を積極的には出さないため、私たち自身で情報を得なければなりません。まずは正確な情報を得ることが大事です。より多くの人たちと正確な情報を共有していき、さらに行政にも働きかけたいと考えています。
そうした視点から、自分たちがどのような場所に暮らしているのかを知る方法として、村内の核や再処理施設の詳細な情報を地図(核のゴミMAP)にして村民に広めています。
また情報提供のため機関紙「リリウム通信」の配布活動にも取り組んでいます。専門家の講演会やアンケートなどを通して、ねばり強い対話で多くの人に危険を認識してもらおうと計画しています。こうしたさまざまな活動を通して、どうしたら原発立地自治体が原発依存から抜け出せるかを常に模索しています。
結果・成果
完了報告・研究成果発表会資料より
リリウムの会では、再稼働に前向きな商工業者が集まる会合にも参加し、意見交換をしたり、東海村を一緒に盛り上げていけるよう、各種イベントやボランティア活動にも積極的に参加しています。原発にただ反対するだけでは、住民に聞く耳を持ってもらえないという苦い経験から、地域の中に入ってまず私たちの人柄を知ってもらうところから始めようと思ったからです。原発を推進する声も再稼働に反対の声もある中で、次のステップに進むためには、住民同士の対話の場が必要で、違う意見を持つからといって批判し合っていても気持ちを傷つけあうだけで前には進めないと感じています。原発が止まることへの不安を抱えている方の思いを丁寧に聞き取り、解決に向けて力をあわせること、それが今求められていると思います。原発に頼らなくてもやっていけるという、地域としての力をつけていくことで、安心して原発を手放せる時が早くなると思います。
2014年7月には、原発を推進する人と反対する人とが一緒になって、東海村の未来について考える場が欲しいと思い、『脱原発で地元経済は破綻しない』などの著書のある、関西学院大学教授の朴勝俊さんをお招きして、「原発地元の未来を一緒に考えよう」と題した講演会を、東海村の後援も得て開催しました。朴先生は講演の中で「原発地元の人々にとって、事故は『確率的(起こらないかもしれない)』だが、失業は『確実』。一緒に考えないと!」と提案していて、とても共鳴しました。原発を推進する方からは、「原発に反対する人が主催する講演は批判的な内容が多いけど、朴先生のような切り口は初めてだ。とてもいい内容だった」と感想をいただきました。
川内原発の地元合意がなされた直後の2014 年11月に、機関紙『リリウム通信』第7号を発行し、全村配付をしました。国が思う地元合意とはこういう流れだということを住民に知らせたくて、安全審査の合格から鹿児島県知事が合意する流れを分かりやすく時系列にして載せました。『リリウム通信』を発行してから、「原発問題について知る機会を得られた」「届くたびに丁寧に読み込んでいる」「本来は行政が伝えるべきことを市民団体がこうして伝えてくれてありがたい」などの反響をいただいています。『リリウム通信』は大きな役割があると思うので、これからも住民に伝わる紙面づくりに努力したいと思っています。
その他/備考