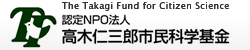第19期(2020年度)国内調査研究助成
書類選考通過者(受付順)
|
受付 番号 | グループ名 代表者名 | テーマ | 応募 金額 | 公開 プレゼン |
| 調査研究助成(一般) | ||||
| 191-003 |
中皮腫サポートキャラバン隊 鈴木 江郎さん |
中皮腫患者に対するピアサポート活動と石綿ばく露調査 | 100万円 | ○ |
| 191-005 |
原発報道・検証室 裁判文書・政府事故調文書アーカイブプロジェクト 添田 孝史さん |
東電原発事故の裁判資料や政府事故調資料の公開データベース作成 | 80万円 | ○ |
| 191-011 |
福島県有機農業ネットワーク 浅見 彰宏さん |
日本人における除草剤成分グリフォサートの暴露実態と有機食材によるデトックス効果の検証 | 100万円 | ○ |
| 191-012 | 八塚 春名さん | 原子力災害後の木灰利用と流通の課題克服に向けた実証的研究 | 100万円 | ○ |
| 191-013 |
インパール作戦後の和解を考える会 木村 真希子さん |
インド北東部マニプル州・ナガランド州におけるインパール作戦と和解――知られざる被害と果たされなかった戦後補償 | 100万円 | ※1 |
| 191-014 |
国連小農宣言・家族農業の10年連絡会 松平 尚也さん |
国連小農権利宣言・家族農業の10年を受けた日本の小農・家族農家による政策提言強化のための調査研究 | 100万円 | ○ |
| 191-015 | 大久保 奈弥さん | 白保と竹富のリゾートホテル建設計画地域付近の海域に生息する生物リストの作成 | 82万円 | ○ |
| 191-018 | 高野 聡さん | 韓国・使用済み核燃料再検討委員会の進行過程における社会運動団体の脱原発フレーム拡張に関する研究 | 73万円 | ○ |
| 191-019 |
空気汚染による健康影響を考える会 山本 海さん |
柔軟剤や洗剤等の家庭用品から放散される微小粒子状物質の定性分析 | 50万円 | ※1 |
| 【調査研究助成(一般応募)小計】 | 785万円 | |||
| 調査研究助成(継続) | ||||
| 196-001 |
太平洋核被災支援センター 橋元 陽一さん |
太平洋核実験による放射線被災実態を解明し、被災船員救済のための研究をすすめる | 50万円 | ※1 |
| 196-002 |
放射能市民測定室・九州(Qベク) 大木 和彦さん |
イメージングプレートを使用するQベク放射能可視化部門の立上げと、土壌中の放射性物質の可視化の提案 | 25万円 | ※1 |
| 196-003 |
いばらき環境放射線モニタリングプロジェクト 天野 光さん |
福島原発事故による茨城県等の放射能長期汚染とその特徴(3) | 40万円 | ※1 |
| 196-004 |
RITA-Congo 華井 和代さん |
コンゴにおける資源採掘と人権侵害の実態調査 | 50万円 | ○ |
| 196-005 |
諫早湾調整池アオコ毒素研究チーム 高橋 徹さん |
諫早湾調整池から有明海に排出されたアオコ毒ミクロシスチンの残留、分解と水生生物への蓄積 | 50万円 | ○ |
| 196-006 |
メコン・ウォッチ 木口 由香さん |
メコン河流域国における開発事業に伴う人権侵害調査 | 50万円 | ○ |
| 196-007 |
放射能を含む廃棄物から子供たちと大久保の自然を守る住民の会 北澤 勤さん |
放射性物質を含む廃棄物処分場予定地周辺の住民参加型環境調査 | 40万円 | ※1 |
| 196-008 |
FoE Japan 森林チーム 三柴 淳一さん |
宮崎県の違法伐採(盗伐)が及ぼす環境社会影響に関する調査研究 | 50万円 | ○ |
| 【調査研究助成(継続)小計】 | 355万円 | |||
| 若手研究支援 | ||||
| 197-001 | 境 翔悟さん | 中山間地域における生活用水の変遷 -水道未普及地域における飲料水供給施設の持続的な管理・運営手法の検討 | 29万円 | ○ |
| 197-002 | 杉山 沙織さん | 地域森林管理を担う林業技術者のキャリア形成-知識・スキルの習得と信念の醸成過程- | 30万円 | ○ |
| 191-004 | 鳥谷部 壌さん | メコン河流域における大規模ダム開発と国際法の支配―事前通報・協議プロセスを中心とする手続的規律の展開― | 100万円 | ○ ※2 |
| 191-010 | 山﨑 真帆さん | 津波被災地域における大規模復興公共事業の「その後」についての調査研究 | 38万円 | ○ ※2 |
| 【若手研究支援小計】 | 197万円 | |||
| 【調査研究助成合計】 | 1,337万円 | |||
※1 公開プレゼンテーションの時間が限られているため、過去の助成研究の内容や、申請者の
事情などから、別途理事会で面接を行うこととしました。
※2 応募内容および全体的な選考の状況から、若手研究支援枠での書類選考通過とすること
にしました。